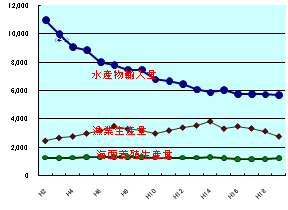トップページ > (業務案内) > 水産施設設計 > 増養殖施設分野

増養殖施設分野
毎年生産されるわが国における水産種苗(稚魚・稚貝など)は、80種あまりに及びます。 ヒラメ・マダイ・ハタハタなど魚類をはじめクルマエビ・ガザミなど甲殻類、ホタテ・アワヒ゛などの貝類、さらにウニ・ナマコなどそれぞれ全国の地先に放流されています。また、ブリ・ヒラメ・クルマエビなどに代表される養殖業も長年生産の重要な役割を担ってきました。
生産魚種と生産量は世界有数規模
|
|
| 放流を主体とした栽培漁業の初めての生産・放流は、社団法人瀬戸内海栽培漁業協会により、昭和38年に瀬戸内海にてマダイ等を対象魚種として行われました。その後、日本各地の種苗生産機関で様々な有用水産動物を対象として技術開発が行われるようになりました。 |  |
※出典:(独)水産総合研究センター「平成17年度栽培漁業種苗生産,入手・放流実績」より
※天然採補種苗のハマチやカンパチ、マアジ、クロマグロなどは含まれておりません。
養殖が支える漁業生産と逼迫する水産物
|
わが国の漁業生産はここ20年で約半分に落ち込み・需要の半分を輸入と養殖に依存しています。ただ、これも中国の経済発展や世界的な健康志向の中で、輸入による確保も陰りが見えてきました。
|
|